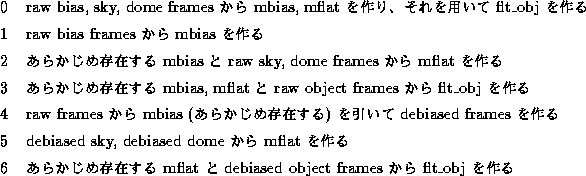
適当な directory に行って、run_flat とタイプするとflat fielding のいくつかの task のうちどれを行うかを聞いてくるので、番号で答えて下さい.
RUN_FLAT
version: June 24, 1993
-----------------------------------------------------
running mode
-----------------------------------------------------
<0> perform whole proceess
(I) raw bias, raw sky, raw dome, raw obj
(O) mbias, mflat, flt_obj
1 make mbias
(I) raw bias
(O) mbias
2 make mflat
(I) raw sky, raw dome, mbias
(O) mflat
3 make flt_obj
(I) raw obj, mbias, mflat
(O) flt_obj
4 subtract mbias
(I) raw obj, mbias
(O) debiased obj
5 make mflat
(I) debiased sky, debiased dome
(O) mflat
6 make flt_obj
(I) debiased obj, mflat
(O) flt_obj
-----------------------------------------------------
[0] is divided into [1, 2, 3] or [1, 4, 5, 6]
Input number (0-6) <default=0> :
各番号は、
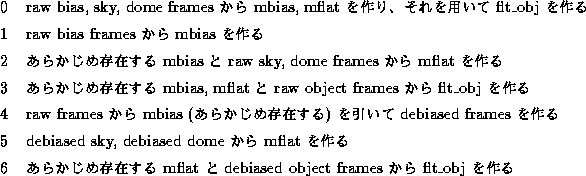
を意味します。デフォルトは 0 です.
, 5, 6 が必要な理由は次の通りです: ある観測夜の sky があまりに少ないと、その夜の sky だけでは精度ある mflat を作れません. そこで他の観測夜の sky も援用する必要がでてきます. ところが観測夜が異なると bias も違ってくるので、援用する sky はあらかじめその観測夜の mbias を引いておかなくてはなりません. すなわち、いくつかの観測夜のデータを合わせて 1 つの mflat を作る手順は、
(1) 観測夜ごとの mbias を作る
(2) 同じ夜の mbias を用いて debiased sky, debiased object を作る
(3) 全ての debiased sky を 1 つの directory に入れる
(4) それを用いて共用の mflat を作る
(5) 全ての debiased objects を 1 つの directory に入れる
(6) mflat と debiased object から flt_obj を作る
となります。この手順に相当するのが、最初に挙げた task のリストの 1, 4, 5, 6 です. ただし、(3) と (5) は自分でおこなってください.
1 - 6 の番号を選んだあとは、入力、出力 frames の directory、 frame name、chip number などを聞いてくるので、入れてください. この flat の直前のバージョンのように editor が立ち上がることはありません. 最初の run_flat のようにUNIX のコマンド入力に似せた形式になっています. mflat を作る際の free parameters は 8 つあります.
# SCCS-ID @(#)PARAM.FILE 1.1 06/25/93 15:21:40 5 mfilter_(used_when_skynum<=skymin) default=5 3 highfilter_(pixels) default=3 15 skymin default=15 5.0 rej_(sigma) default=5.0 50 skymesh_(pixels) default=50 2.5 rej_local_(sigma) default=2.5 2.5 rej_pdev_(sigma) default=2.5 1.0 gaussigma_(pixels) default=1.0
このうちのいくつかについて説明しておきましょう.
(1) mfilter (default = 5 pixels)
sky の枚数が少ないと、星の影響を少なくするために msky にある程度の median filterをかける必要があります.
mfilter とはこの median filter の半値幅 (単位は pixels) です.
正確には、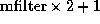 が median filter の幅になります.
この median filter は、sky の枚数が skymin 以下のときに限り実行します.
skymin も free parameter です ((3) を見よ).
が median filter の幅になります.
この median filter は、sky の枚数が skymin 以下のときに限り実行します.
skymin も free parameter です ((3) を見よ).
(2) highfilter (default = 1 pixel)
mflat に使用する sky は、多くの場合 object でもあります.
ある pixel の msky を単純に sky の median で求めると、それで object を割ったとき、sky の枚数分の 1 の確率で、自分自身で自分自身を割ることになります.
これを避けるためには mflat の 空間的に high frequency な成分は dome から求めるのがよいのですが、そのためには msky の high frequency 成分を消しておく必要があります.
highfilter とは high frequency を消すための median filter の半値幅です.
mfilter と同様、正確には 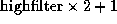 が median filter の幅です.
が median filter の幅です.
(3) skymin (default = 14)
sky の枚数が skymin 以下のときは、msky をある大きさの mesh に区切り、各 mesh 内で ADU カウントがはずれた pixels をその mesh 内の pixels の median でおきかえます. その後 mfilter の半値幅で median smoothing を行います. mesh の大きさは skymesh で指定します.
(4) skymesh (default = 100 pixels)
sky の枚数が skymin 以下のときは、 msky を mesh に区切り各 mesh 内ではずれた pixels を mesh 内の median でおきかえます ((3) を見よ). この mesh の一辺の長さ (単位 pixels) を skymesh で指定します.
(5) rej_local (default = 2.5  )
)
sky の枚数が skymin 以下のときは、 msky を mesh に区切り各 mesh 内ではずれた pixels を mesh 内の median でおきかえます ((3) を見よ). このおきかえの基準を与えるのが rej_local です. すなわち、ある pixel がその mesh 内の pixels の median から rms の rej_local 倍以上はずれていればおきかえをします.
これらはデフォルト値でいいと思います. ただし、skymin は、星の少ない場所であれば、10 でも大丈夫でしょう. 1 つの観測期間全ての sky を合わせて mflat を作るのであれば、殆どの場合 15 枚以上の sky があるはずです.